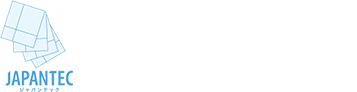法人工場向け:定期メンテナンス計画の立て方と実践的PDCA運用事例
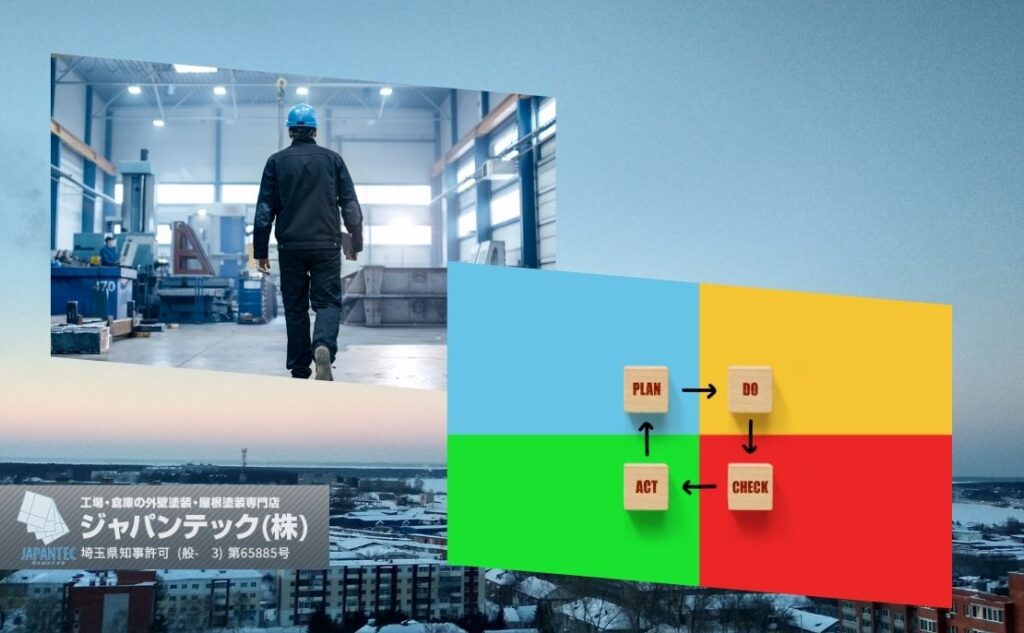
春日部市、越谷市、さいたま市の工場を中心に外壁塗装工事・屋根塗装工事、リフォーム工事を専門にしている
工場・倉庫の外壁塗装・屋根塗装専門店ジャパンテック(株)です!
代表取締役の奈良部です!
多くの工場で「設備が壊れてから修理する」が当たり前になっていませんか?
実際、突発的な故障で生産ラインが止まり、納期遅延や重大事故に発展するケースは後を絶ちません。
一方で
「メンテナンスは必要だと分かっていても、計画の立て方が分からない…」
「予算が確保できない…」
といった悩みを抱える現場責任者や経営層も多いのが実情です。
定期メンテナンスは、工場の設備や建物を「壊れない状態で維持し続ける」ための仕組みであり、単なる点検表作成ではありません。目的はあくまで、生産の安定・コスト削減・リスク回避です。
今回のお役立ちコラムでは「法人工場向け:定期メンテナンス計画の立て方と実践的PDCA運用事例」について、現場と経営をつなぐ視点から具体的に解説します。
▼合わせて読みたい▼
工場塗装と戸建て塗装の共通点とは?|失敗しない業者選びのために押さえておくべき基準とは
なぜ定期メンテナンスが必要なのか

「修理すれば済む」「まだ動いているから問題ない」
このような考え方は、目先の手間やコストを減らすように見えて、実は経営リスクを見過ごしている危険な判断です。ここでは、定期メンテナンスがなぜ今、重視されるのかを3つの観点から明確にしていきます。
工場におけるメンテナンスの目的と効果
工場のメンテナンスは、単なる点検作業ではありません。根本にあるのは「生産の止まらない環境を維持する」という経営目標です。
・設備の故障による突発停止リスクの低減
・製品不良・歩留まり低下の抑制
・従業員の安全確保と労災予防
たとえば、たった1台のコンプレッサーが停止しただけで、空圧ライン全体が止まり、1日あたり数百万円の損失が発生する工場もあります。事前の定期点検でこのリスクを回避できていれば、その損失は限りなくゼロに近づきます。メンテナンスは「余計なコスト」ではなく「確実な利益保全策」なのです。
放置による設備・建屋トラブルの事例
メンテナンスを後回しにしてしまったことで、取り返しのつかない事態に発展することもあります。以下は実際の現場で起きた失敗例です。
・【機械設備】老朽ポンプの異音を放置→異常停止→全ライン停止→納期遅延
・【建物】屋根防水の劣化を見逃し→雨漏り→製品廃棄・顧客クレーム発生
・【電気設備】年次点検を怠った結果→盤内トラッキング→発煙・停電
これらの共通点は「兆候はあったのに、判断と対応が遅れた」ということです。予算や人手が足りないことを理由に後回しにしたツケは、想像以上に大きくなる可能性があります。
法定点検・予防保全・状態基準保全の違い
メンテナンス計画を立てるうえで、以下の3種類の保全方法を正しく理解することが重要です。
|
種類 |
内容 |
実施主体 |
特徴 |
|
法定点検 |
法令で義務付けられた点検(例:電気・消防) |
管理者責任 |
実施しないと法的罰則あり |
|
予防保全(PM) |
故障する前に、定期的に点検・交換 |
自主運用 |
故障率を低減する基本対策 |
|
状態基準保全(CBM) |
実際の劣化状態に応じて保全判断を行う |
一部先進工場 |
センサー・履歴による最適保全 |
多くの工場では法定点検が「最低限のメンテナンス」となっていますが、それだけでは不十分です。予防保全を標準化し、余裕があればCBMも視野に入れることで、コストを抑えながらも故障リスクを最小化できます。
とくに、設備投資の頻度を減らしたい中小規模工場では「予測」と「未然防止」に基づく仕組み作りが重要です。
▼合わせて読みたい▼
工場の美観の低下は集客力の低下に影響する!?美観向上で集客に相乗効果を生む5つの理由
実践的メンテナンス計画の立て方と予算設計

「メンテナンス計画を立てろ」と言われても、白紙の状態から作るのは現場にとって非常にハードルが高い作業です。点検周期の設定、対象の選定、年間予算の確保、そして社内合意形成。
これらを一貫したロジックでまとめるには、単なるエクセル管理だけでは不十分です。
点検周期の設計と優先順位の付け方
メンテナンス計画の出発点は「何を・どの頻度で・どの順番で点検するか」の設計です。まずは以下の3軸で優先順位を明確にしましょう。
・クリティカル度:止まると工場全体に影響が出る設備か
・使用頻度:24時間稼働か、スポット運用か
・老朽化度:設置からの経過年数、過去の不具合履歴
これを「設備マップ」に可視化し、年次/月次/週次などの周期でカテゴリごとに整理するのが現実的です。
・空調設備 → 年1回(冷暖房切替時)
・給排水・配管 → 半年ごと(腐食・詰まりの兆候)
・屋上・外壁 → 2〜3年ごとの目視点検+写真記録
さらに、計画の見える化にはカレンダー形式が有効です。年度単位でどの月にどの設備を見るかが一目でわかれば、属人化を防ぎ、部門間でも共有しやすくなります。
年間予算の立案とコストマネジメント
メンテナンスは「予算がなければできない」ではなく「予算枠を確保してこそ実行できる」活動です。まずは過去3年分の修繕履歴とコストを棚卸しし、下記のように整理しましょう。
|
区分 |
内容 |
予算枠設定の目安 |
|
定期メンテ |
計画に基づき実施する点検・交換 |
年間の定額(予測可能) |
|
突発修繕 |
故障対応、緊急補修など |
全体予算の15〜20%をバッファに設定 |
|
改修・投資枠 |
大型改修や老朽設備の更新 |
別枠で稟議、または3年計画で分割対応 |
また、経営層に理解してもらうためには「設備延命による償却効果」や「ダウンタイム削減による利益確保」といった、数字で見せる説得材料が重要です。
単に「修理が必要です」ではなく「壊れる前に直すことでどれくらいの損失を回避できます」と伝えることで、予算承認のハードルが下がります。
経営層と現場の認識ギャップを埋める工夫
メンテナンス計画は、現場だけでは完結しません。最終的に予算を承認するのは経営層であり、理解と納得を得るための翻訳力が求められます。そこで意識すべきは以下のポイントです。
・点検記録 → 提案書 → 稟議資料への変換プロセスを確立
・専門用語ではなく「経営目線のリスクと利益」で説明
・改善提案や省エネ効果も含めたプラスの要素を織り込む
たとえば「床の剥がれを補修しないとフォークリフトが滑って事故につながる」ではなく「補修すれば労災リスクを減らし、結果として保険料や労務コストの削減につながる」と伝えることで、経営層の意思決定スピードが上がります。
PDCAを現場に根付かせる運用の工夫

どれだけ優れたメンテナンス計画を立てても、それを実際に回し続ける仕組みがなければ絵に描いた餅です。特に工場のような多忙な現場では「毎日の生産対応で手一杯」「点検記録が残らない」「改善がルーチン化しない」といった運用崩壊が起こりがちです。
PDCAサイクルを単なる理論ではなく、現場に定着させるための具体的な運用術を紹介します。
Plan(計画):実働ベースで作る年間スケジュール
「年間点検計画はあるけど、誰も見ていない」。そんな状態に陥っていないでしょうか?形骸化させないためには、現場の実働に合わせた生きたスケジュールを作ることが前提です。
・ExcelやGoogleスプレッドシートで月別タスク表を作成
・建物・設備ごとにシートを分け、部門別に管理
・点検対象に「担当者」「期日」「完了チェック欄」を設置
加えて、資材や部品の調達・業者依頼のリードタイムも考慮した準備期間を前倒しで組み込んでおくことで、実行率は大きく向上します。
たとえば「6月に屋上防水点検」と決めたら、4月中に足場や高所作業車の手配を計画に含める、というレベルの具体性が必要です。
Do(実行):日常点検のルール化と履歴管理
計画だけ立てても、点検作業が人任せになってしまえば、内容のばらつきや記録漏れが起こります。だからこそ、作業の「仕組み化」と「見える化」が不可欠です。
・担当者を固定せず「班単位」「時間帯単位」での分担制
・チェックリストは紙ではなくスマホ・タブレットで入力
・撮影画像+チェック項目をクラウド共有(Google Drive、Boxなど)
ここで重要なのが「異常がなかったこと」も記録に残すこと。異常時のみ報告する運用では、逆に普段何を見ていたのかが後で分からなくなります。履歴を残せば、過去との比較や設備の劣化傾向の把握にも活かせます。
Check / Action:記録の分析と改善反映の仕組み
最後に、多くの現場がつまずくのが「分析と改善」です。「点検結果は記録したけど、その後は誰も見ていない」という状態では、何も変わりません。ここを突破するには、月1回のレビュー会議+改善提案の仕組み化が有効です。
・点検・修繕履歴を一覧化し、傾向を読み解く(例:●月に集中して故障が多い)
・「同じ部品で何度も不具合」が起きたら、そもそも仕様変更を検討
・改善案は提案シートとして提出し、採用されたら評価に反映
さらに、改善提案が社内で共有され、実際に採用されていくサイクルが見えることで、現場のモチベーションにも直結します。形式的な報告会ではなく「現場が主役」の場として位置づけることが重要です。
PDCAは理屈ではありません。「やってみて」「残して」「見直して」「直す」という一連の行動を現場文化に落とし込めるかが、運用の分かれ目です。成功している工場の共通点は、計画書ではなく行動習慣にPDCAが根付いていることにあります。
計画を回すことが現場と経営を強くする
定期メンテナンス計画は、単なる点検スケジュール作成ではありません。
それは、工場の設備・建物の安定稼働を支え、トラブルや損失を未然に防ぐための経営基盤の整備です。
ただし、作って終わりでは意味がありません。大切なのは、計画が現場で実行され、結果が記録され、改善に反映される循環として機能しているかです。どれだけ立派なPDCAが頭にあっても、仕組みとして根付かなければ、いずれ現場に見放されます。
一方で、運用まで設計されたメンテナンス体制は、次のような効果を生み出します。
・突発修理やトラブル対応に追われない守りの強い現場
・予算獲得や稟議が通りやすくなる経営に伝わる仕組み
・点検が属人化せず、誰でも回せる仕組みとしての安心感
もし、まだ「定期点検はしているけど計画とは呼べない」「PDCAが回らない」という状態であれば、まずは年間スケジュールと簡易な記録ルールから始めてみてください。小さな一歩でも、確実に止まらない工場への土台づくりが始まります。
ジャパンテックで始める!工場の定期メンテナンス計画とPDCA運用相談

工場経営の安定と利益確保のためには、「壊れてから修理」ではなく“止めない仕組み”を持つことが最重要です。
工場・倉庫の外壁塗装・屋根塗装専門店ジャパンテック(株)では、法定点検から予防保全、状態基準保全(CBM)まで、現場の実態に合わせた定期メンテナンス計画の立案からPDCA運用までをトータルでサポートしています。
-
何から始めれば良いかわからない
-
予算組みや点検周期の見直しをしたい
-
現場と経営層の認識ギャップを埋めたい
-
記録や改善のPDCAを現場に根付かせたい
こんなお悩みも「ジャパンテック」にご相談ください。初回相談・現地調査・ご提案は無料です。問い合わせフォーム・メール・お電話・ショールーム来店にて、御社に合った“現場で動くメンテナンス体制”づくりを全力でサポートします。まずはお気軽にご相談ください!
『外装劣化診断』はこちらから
お電話でのご相談、お問い合わせはこちら
フリーダイヤル:0120-605-586
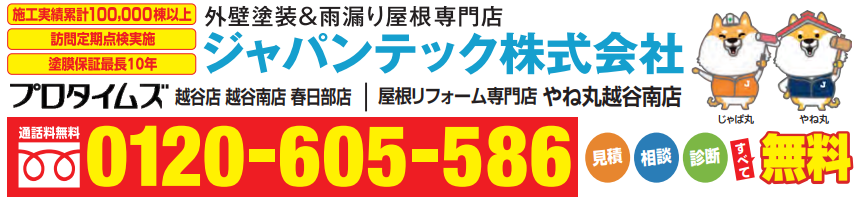
越谷市、春日部市の外壁塗装・屋根塗装リフォームのご相談は
プロタイムズ越谷店・プロタイムズ春日部店・プロタイムズ越谷南店へ!!