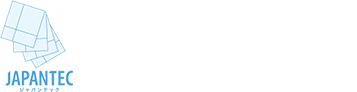金属サイディングの白錆・赤錆対策:素地処理と下塗

春日部市、越谷市、さいたま市の工場を中心に外壁塗装工事・屋根塗装工事、リフォーム工事を専門にしている
工場・倉庫の外壁塗装・屋根塗装専門店ジャパンテック(株)です!
代表取締役の奈良部です!
金属サイディングは、デザイン性と耐久性を兼ね備えた外壁材です。そのため多くの工場・倉庫・住まいで採用されています。ただしメンテナンスを怠ると「白錆」や「赤錆」といった腐食現象が発生し、短期間で劣化が進むこともある素材です。とくにガルバリウム鋼板などのメッキ系素材は、一見強そうに見えても、表面の防錆皮膜が破壊されると、腐食が急速に拡大することもあります。
錆による腐食の進行を止めるためには、再発しないように長期耐久仕様を自ら判断できる力が必要です。初期対応の重要性を理解し、適切な下塗り選定を行えば、金属サイディングの寿命を10年以上延ばすノウハウが得られます。
そこで今回のお役立ちコラムでは、白錆・赤錆の発生メカニズムから、正しい素地処理・下塗り選定・検査方法までくわしくお話しします。
▼合わせて読みたい▼
工場の美観の低下は集客力の低下に影響する!?美観向上で集客に相乗効果を生む5つの理由
白錆・赤錆が発生する原因と進行メカニズム
金属サイディングの腐食は、目に見えない初期段階から進行するため、発生原因を理解することが対策の第一歩です。
白錆とは何か?表面の酸化現象
白錆はアルミ亜鉛メッキ層が、長時間湿潤環境にさらされた際に発生します。簡単に乾燥しない環境で、水分や塩分の影響で亜鉛が酸化し、表面に白い粉状物(酸化亜鉛)が生成される現象です。
白錆の発生には必ず水分が関係します。ただ、雨水や飛沫だけでなく、結露が原因となる場合も見られるのです。初期の白錆は一見軽微に見えますが、防錆皮膜を破壊します、そのため、下層の鋼板が酸化しやすくなるのです。進行を放置するとメッキ層が剥離し、赤錆へと変化します。
赤錆とは?酸化が鉄素地まで達した状態
メッキの防錆作用が失われると、腐食は進行しわずか1〜2年程度でも孔食に至る場合もあります。とくに北面や軒裏など、乾燥しにくい部位で発生しやすく、早期に処置しなければ建物全体の劣化を招くのです。
赤錆は、表層だけでなく内部構造にまで影響を及ぼします。腐食が進行すると、金属の強度が低下し、外壁パネルの浮きやビスの抜け、さらには雨水の浸入による内部断熱材の劣化にもつながるのです。鉄骨構造では、局所的な赤錆が構造耐久性を損なう危険もあるため、早期の補修が不可欠です。
白錆・赤錆が発生しやすい環境と現場兆候

発生しやすい環境を特定し、兆候を早期に発見することで、補修コストと損害を最小限に抑えられます。
リスクの高い立地・気候条件
リスクの高い立地・気候条件としては、海岸から2km以内の沿岸部や湿度の高い山間部・盆地などがあげられます。そのほか、冬季の寒暖差が激しい地域も要注意です。このような環境下では、塩害・結露・凍結融解といった現象が繰り返され、塗膜やメッキ層に微細な亀裂を生じさせます。その結果、雨水や空気中の酸素が内部に侵入し、短期間で酸化が進行するのです。
とくに北面や日陰部分、軒裏・水切り下部・ボルト周辺は乾きにくく、錆が潜行的に広がりやすくなります。さらに、雨風の吹き上げが強い立地や積雪地域では、メッキ層の剥離速度が加速し、早ければ5年以内で腐食が目立つ場合もあるのです。そのため、立地環境にあわせた防錆塗料選定やメンテナンス計画が不可欠です。
劣化サインの見極め
塗膜の浮き・変色・粉状の白化物が初期段階の警告サインです。さらに、指でなぞると粉が取れたり金具に黒ずみがあったりすると注意が求められます。雨筋に茶色い跡が出てきた場合は、酸化が進行している証拠です。
とくに金具固定部やジョイント周辺で膨れや剥離が見られた場合、すでに防錆層が破壊されている可能性も高く、素地処理+防錆下塗りによる早期対応が不可欠となります。また、サイディングの裏側や重ね継ぎ目の隙間に湿気がこもると、表面は健全でも内部で錆が進行している可能性もあるのです。見た目だけでは判断が難しいため、赤外線カメラや導電テスターによる非破壊診断を行うと劣化範囲を正確に把握できます。
とくに工場・倉庫の高所壁面や機械排気口付近では、温湿度差による局部腐食が多発するため、定期点検時の重点チェックポイントとしての記録が重要です。
白錆・赤錆の実務的処置手順

適切な処理手順を踏むことで、再発を防ぎ、塗膜の密着性を最大限に高められます。
素地調整と下地洗浄|腐食を止める初動工程
金属サイディングの補修では、まず腐食部を完全に除去することが最優先です。白錆・赤錆が出ている部分は「サンドペーパー・ワイヤーブラシ・電動ケレン」などを使い、金属光沢が出るまで研磨します。この工程を省くと、下地に錆が残り、塗膜下で再腐食が進行するのです。
除去後は、粉塵や油脂を取り除いて弱溶剤シンナーで拭き上げ、清潔な状態を確保します。そのうえで、完全乾燥させることが重要です。湿潤状態で塗装すると、白化・ブリード・密着不良の原因となります。
防錆下塗り| 錆進行度に応じたプライマー選定
下塗り材は、錆の進行具合に応じて適切な防錆プライマーを選びます。白錆の段階では、亜鉛粉末入りジンクリッチプライマーを使用すると、電気化学的な防食作用が得られます。
一方、赤錆が進行している場合は、エポキシ樹脂系防錆プライマーが有効です。これにより、金属表面に不動態皮膜を形成し、酸化を化学的に抑制できます。
下塗りの均一性が後工程の密着性と耐久性を左右するため、塗布量と膜厚管理の徹底が必要です。
中塗り・上塗りと検査 ― 耐候性・品質を保証する最終工程
仕上げ塗装には、温度変化や膨張・収縮に強いウレタン系またはフッ素系塗料を選定します。とくに屋外環境にさらされる部位には遮熱性塗料が有効です。併用することで屋根・外壁表面温度を10〜15℃下げられるため、錆進行の抑制につながるのです。
施工完了後は、膜厚計による膜厚確認とJIS K5600-5-6(クロスカット法)による付着試験を実施します。
さらに施工写真・試験記録を報告書として保存し、保証書発行時の根拠資料とするのも有効です。企業としての品質証明と信頼性を確保できます。
参照:国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版
点検周期とメンテナンス
外壁サイディングの耐久性は、塗膜によって大きく左右されます。再塗装は一般地域で10〜12年、海風・結露・寒暖差の大きい地域では7〜8年周期が理想です。
とくに金具部や水切り下部など、雨水が溜まりやすい箇所を重点的に点検します。白錆・膨れ・変色などの初期症状を早期に補修することで、腐食拡大を防止できるのです。点検記録を残しておくと、次回改修時に塗膜の劣化傾向を把握でき、補修計画の精度が高まります。
また、点検は春(梅雨前)と秋(台風後)の年2回実施するのが理想的です。季節ごとの温度差や湿度変化による膨張・収縮を観察することで、塗膜の早期劣化を見逃さずに済みます。あわせて、排水経路やコーキングの状態も確認し、漏水や錆再発の兆候を見つけたら、軽微なうちに部分補修を行うことが長寿命化の鍵となるのです。
重症腐食時の対応 ― 張替え・カバー工法の判断基準
赤錆が裏面に到達している場合、塗装補修では延命できません。鋼板厚が0.3mmを下回ると強度が保てず、張り替えが必要です。ALC・木造どちらの下地でも、腐食部を撤去し、防水層を再構築してから新規外壁を取り付けます。軽度な腐食なら、既存外壁を残したまま上から金属サイディングを重ねるカバー工法が有効です。工期短縮・廃材削減・遮熱性向上など複合的なメリットがあり、工場や倉庫でも多く採用されています。
腐食を防ぐのは初期対応と下塗り選定
白錆や微細な膨れは、表面だけでなく内部腐食のサインです。早期に研磨・防錆プライマー塗布を行えば、腐食進行を止められます。とくに、エポキシ系・ジンクリッチ系プライマーの選定が耐久性を左右します。
施工時には湿度・気温を記録し、乾燥時間を守ることが重要です。また、JIS K 5600試験や国交省「公共建築工事標準仕様書」に準じた検査を実施し、膜厚・付着強度を確認することで、長期防食性能を裏付けられます。
FAQ:よくある質問

Q1:白錆は洗浄だけで止まりますか?
A.軽度であれば一時的に除去可能ですが、再発防止には防錆プライマーでの封じ込みが必須です。研磨と乾燥も求められます。
Q2:錆転換剤と防錆プライマーの違いは?
A.錆転換剤は軽度酸化を黒色化して安定化させますが、進行錆には不十分です。エポキシ防錆下塗りをすると、再酸化を防ぐ化学皮膜が形成されるため耐久性も高くなります。
Q3:再塗装の目安周期は?
A.環境条件によりますが、一般地域で10〜12年、沿岸部で7〜8年です。定期点検で早期発見が重要です。記録を残すのも後々を考えると安心できます。
Q4:保証は適用されますか?
A.多くのメーカー保証では、施工時に錆が残存していた場合は対象外です。施工前写真や報告書を残しておくことで、後の保証トラブルを防げます。
ジャパンテックに相談|白錆・赤錆を止める最短ルートは“素地処理+最適下塗り”の設計力

金属サイディングの劣化は見た目の塗り直しでは止まりません。検索意図の答えは「再発しない下地づくり」です。白錆は水分環境での亜鉛酸化、赤錆は素地鉄まで酸化が進んだ状態。だからこそ最優先は研磨・脱脂・乾燥の徹底と、腐食度に応じた下塗り選定です。
工場・倉庫の外壁塗装・屋根塗装専門店ジャパンテック(株)は電動ケレンで金属光沢まで戻し、白錆域はジンクリッチ、赤錆域はエポキシ系防錆でゾーニング塗装。膜厚・付着はJIS K5600準拠で実測管理し、報告書と保証に紐づけます。沿岸・結露・排気周辺など高リスク部は遮熱上塗りで表面温度を下げ腐食速度を抑制。張替えやカバー判断が必要な重症域も、導電テスターと赤外線で可視化しLCCで最適解を提示します。
法人の皆さま、まずは現況診断と仕様比較からご依頼ください。お問い合わせフォーム・メール・電話でのご相談を常時受付中。ショールームでは下塗りサンプルや遮熱デモをご体感いただけます。
ジャパンテックが貴社の稼働条件と環境負荷に合わせ、錆の再発を抑える長期耐久仕様をご提案します。
▼合わせて読みたい▼
『外装劣化診断』はこちらから
お電話でのご相談、お問い合わせはこちら
フリーダイヤル:0120-605-586

越谷市、春日部市の外壁塗装・屋根塗装リフォームのご相談は
プロタイムズ越谷店・プロタイムズ春日部店・プロタイムズ越谷南店へ!!